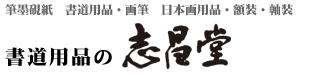熊野筆について、また墨、和紙、硯など書道に関する知識を紹介しています。ここにないことでも何かご質問がありましたら、志昌堂製品取り扱い店、または、メールフォーム・お電話にてお問い合わせ下さい。
筆はどんなに安い筆でも、全て職人による手作りです。ぜひこちらで匠の技をご覧下さい。
「写真提供:広島県安芸郡熊野町役場」

工程1 選毛・毛組み
毛の善し悪しを選別し、使う毛と使わない毛とに仕分けします。

工程2 火のし・毛もみ
灰をまぶし、火のしをあてた毛に鹿皮を巻いてもみます。毛の油を抜き取り、墨含みを良くするための工程です。

工程3 毛そろえ
クシ抜きして綿毛を取り除いたあと、少量ずつ毛を積み重ね毛をそろえてゆきます。

工程4 逆毛・すれ毛取り
毛先を完全にそろえ、小刀で逆毛・すれ毛等を指先の感触を働かせながら抜き取ります。

工程5 寸切り
命毛・のど・腹・腰とよばれる筆の先端から下部にかけての毛を、それぞれの長さに切り分けます。

工程6 練り交ぜ
寸切りした毛を薄く広げ、交ぜあわせてゆきます。残っている逆毛等を取り除いたあと、完全に交ぜて薄糊をつけます。

工程7 芯立て
芯立筒(コマ)に毛を入れ、太さを規格に合わせます。不必要な毛をさらに抜き取り、乾燥させます。

工程8 衣毛(上毛)巻き
衣毛(芯より上質の毛)を薄く広げて乾いた芯に巻きつけ、さらに乾燥させます。

工程9 糸締め
毛の根元を麻糸で結び、焼きごてをあて素早くまとめます。筆の穂首(毛の部分)のできあがりです。

工程10 くり込み
穂首を軸にはめ込み、接着剤でしっかりと固定します。

工程11 仕上げ
糊を穂首に含ませたあと、巻きつけた糸を回しながら余分な糊をとり除きます。穂首の型を整えたら乾燥させ、キャップをはめます。

工程12 銘彫刻
軸の部分に三角刀で銘を彫ります。こうして一本の筆が完成しました。

(1)選びかた
毛筆には主に、羊(やぎ)、馬、たぬき、いたちなどの毛が使われますが、毛の質やその硬さ・柔らかさは、どのような動物のどの部位の毛を使うか、また、どの産地のものを選ぶかによってさまざまです。
一般的に良い筆とは、毛の一本一本がすなおでよく揃っていること、穂がふっくらしていること、穂先が鋭いこと、弾性に富むことなどが要求されますが、ときには一頭分の毛から一本の筆しかできないほど、毛の質を吟味することもあるそうです。
一本一本の毛は、根元から先に向かって徐々に細くなり、先がとがってまっすぐなものがよく、それらを集め、束ねて穂を作るわけですから、筆穂を固めてみると、円すい型で根元から穂先に向かって徐々に細くなっているものがバランスのよい筆で、中間が太目になっていたり、穂先が急に細くなっているものや、ちぢれ毛のまじっているものなどは、良い筆とはいえません。
(2)種類
毛筆は毛の硬さによって、大きく三種類に分類されています。
1.羊毛筆
いちばん柔らかい筆が羊毛筆です。この筆は非常に腰が柔らかく、墨の含みがよく、筆の代表的なものですが、初心者には使いこなしがむずかしく、専門家用の筆といってもよいでしょう。
2. 兼毫(けんごう)筆
一般に最も多く用いられるのが兼毫筆で、柔らかい羊毛から、いたち、たぬき、鹿、硬い馬の脇毛などをまぜて作ったものです。墨の含みがよく、腰も強く扱いやすいので、初心者から専門家まで幅広く用いられています。
3. 剛毫(ごうもう)筆
最も硬いものが剛毫筆で、極めて腰が強いので扱いやすく、子供の書写用や初心者向けの筆として多く用いられています。
(3)特性
筆穂の長さには、長鋒、中鋒、短鋒の三種があり、太さについては、それぞれ号数で区別していますが、書く作品の目的にかなった筆をみつけ出すようにしましょう。
硬い筆のほうが腰が強くて扱いやすく、初心者向けの筆ですが、この硬い筆に慣れてしまうと、柔らかい羊毛筆などを扱う技術がいつまでたっても身につかないものです。筆使いに慣れるに従って、だんだん柔らかい筆も使いこなせるようにならなければなりません。つまり筆の柔剛の差は、筆使いの難易度にかかわりなく、表現のねらいによって使いわけるもので、いずれの毛の特性にも対応できる筆使いができるように修練する必要があります。
なお筆を長持ちさせるには、筆穂を「洗う」というより、水をたっぷり含ませて古紙などでよく拭うようにしておくとよいでしょう。使いっぱなしにして墨が固まってしまうと、どんなよい筆でもたちまち書きにくくなってしまいます。

(1)種類
墨は煤煙(すす)に膠(にかわ)や香料をまぜて固めたもので、原料の種類によって、油煙墨、松煙墨の二種があります。そのほか、工業原料から採取した煤煙で作った工業煙墨もあります。また固形墨のほか、練り墨、墨液、墨汁といった上質の液体墨も盛んに作られています。
墨には油煙と松煙の区別があるとはいえ、原料によって、それぞれの煤煙の性質が異なるため、墨色にも漆墨系、茶系、青系などの差があり、それが書表現に大きな影響を与えます。例えば、水墨画や日本画によく使われる青墨(良質の松煙墨)などは水で薄めると実に美しい暗青墨を出します。従って、それぞれの製墨の状況や各種の墨の特色を知っておくことも必要です。
(2)原料
油煙墨は菜種油、胡麻油、大豆油、綿実油などの植物性の油を燃やして採取した煤煙で作るもので、炭素の粒子は細かく、純度が高いので、墨色の厚みはやや劣りますが、光をよく反射しますので、黒光りし、黒さが強く感じられます。
松煙墨は、生きている松(生き松)、松ヤニのたくさん残っている枯れた松(落松)、伐採して十数年たった地中の松の根(根松)などを小割りにして、かまどで燃やして採取した煤煙を原料にします。松煙墨は油煙墨に比べると炭素の粒子が粗く、不純物も多いので、製墨後長期間経つと、だんだん墨色が変化していきますが、光をよく吸収しますので、しっとりした深みのある黒さが特徴です。
工業煙墨は軽油、重油、クレオソート油などの鉱物性の液体油や、粗製ナフタリン、コールタールなどの鉱物性固形油を燃焼させて採取した煤煙に、天然ガスから採ったカーボンブラックを加えて作ったものです。
(3)用法
煤煙で作った墨は、数個の炭素の粒子を膠で包み込んだ粒を固めたものです。この一粒一粒は、ちょうど薄皮饅頭のように、薄い膠の皮膜で被われた状態ですから、墨を下ろすということは、水を使って、この集合体をバラバラにすることです。この過程で、炭素粒子を包んでいる膠の膜が水に溶けてしまうと、膠がコロイド状になって炭素が遊離し、どろどろの伸びの悪い、つまり浸透性の悪い墨水になってしまいます。この現象は、湯で墨を下ろしたり、力を入れて磨りすぎたり、あるいは長期間墨水を放置した場合(宿墨という)などに起こります。数百年も経た古墨がよいといわれるのは、膠が枯れて溶けにくくなっているためです。いずれにしても、膠の膜の破れていない墨水は、たとえ濃墨であっても、サラっとしていて、墨の伸びもよく、美しい墨色を呈します。このような状態の墨水を活墨といい、どろどろに粘った墨水を死墨といいます。美しい墨色を得るために、質の高い墨を選ぶこともさることながら、下墨の方法にも留意し、良質の硯で、軽く丁寧に下ろすことを心がけるとよいでしょう。

(1)書道用の紙
紙の製法が紀元前に中国で発明されたことは有名ですが、その製法がヨーロッパに伝播するのに実に1000年もの時間を要したこともまた有名です。ヨーロッパに渡った紙の製法は、機械的印刷に耐えられる紙を抄造するために改良され、今日、私たちが紙といえば、ほとんどがこの印刷洋紙のことを指すほどに普及しました。しかし、中国では紙に毛筆で文字を書いたため、その効果をより上げるための抄造法の研究が重ねられ、今日に至っています。
今日の書道で用いられている紙は、伝統に培われてきたもので、中国製の紙では玉版箋と画仙紙が一般に多く用いられています。
玉版箋は高価なため、あまり一般には用いられませんが、にじむ紙の代表的なもので、書表現にはかけがえのない紙です。にじむ紙に書かれた文字は潤いがあり、多様な表現効果を得ることができますので珍重されますが、そのにじみを自在に制御できるようになるにはかなりの技術の練磨が必要です。
作品を書くのに最も好まれているのが画仙紙です。これは画箋紙、画箋紙、雅箋紙、雅仙紙などとも書き、やはりにじみのある紙です。中国製の画仙紙を「本画仙」、日本製の画仙紙を「和画仙」と呼びます。
墨がにじむのは、紙の吸水性が強く、紙に含まれた墨水が広がっていくためです。紙質によって差がありますが、墨水の濃度がうすくなったり(水分が多くなる)、運筆の速度が遅くなるほど多くにじみます。
いずれにしても、この墨のにじみは書の表現とって非常に重要なもので、画仙紙を用いてその効果を充分に引き出せるよう修練を積むことも、書の勉強にとって大切なことです。
(2)かなの料紙
製紙法が日本に伝わったのは7世紀の初め(聖徳太子の摂政時代)のことで、今日、日本の伝統的な方法で抄造される紙を和紙と呼んでいます。手漉きと機械漉きがありますが、その原料は同じです。
大字かなは別として、かな作品には多く和紙が用いられますが、雁皮、楮、三椏などを適宜混合して抄造した「鳥の子紙」がその代表的なものです。鳥の子紙はにじみの少ない紙で、これに美しい地模様を刷り込んだり、金、銀の砂子をかけたものなどを作り、書表現をより効果的なものにするための料紙が作られています。これがかな料紙です。
このような紙は一般に加工紙と呼ばれていますが、このほかに、にじみを止めるために、礬砂(どーさ)引きといって、明礬(みょうばん)を溶かした水に膠液(にかわえき)を加えたものを素紙に塗布したものも、加工紙と呼びます。
にじみのない紙に文字を書くと、筆路が美しく出て、なかなか捨てがたい味を醸し出してくれるものですが、これが書の表現のすべてではありませんので、自分の表現のねらいに適った紙を的確に選べるよう、いろいろな紙の特性をよく知っておく必要があります。
(3)画仙紙の大きさ
画仙紙にはいろいろな大きさの全判の紙がありますが、一般的には、大画仙(97×180cm)、中画仙(83×150cm)、小画仙(70×135cm)と呼ばれる三種類の紙が多く用いられています。中でも、小画仙の全判の紙を「全紙」と呼び、全紙の縦二分の一を「半切(はんせつ)」、縦四分の一を「聯(れん)」、残りの四分の三を「聯落(れんおち)」と呼んでいます。

(1)種類
硯は中国では紙や筆や墨とならんで、長い歴史を持つ文房具の一つですが、その素材としては、古くは陶、磁、瓦などが使われてきました。唐・宋時代になって、硯に適した石材が発見され、それが非常に優れた機能を発揮することから、それまでのものに替わって石硯として定着し、すっかり硯の主流になりました。今日、硯といえば石硯であると思ってもまちがいないのは、そういう背景があるからです。
中国には広東省産の端渓(たんけい)硯、安徽・江西省産の歙州(きゅうじゅう)硯など、中国には高品質な石脈がありますが、今日では掘りつくされてしまったり、採掘することができなくなってしまったりして、徐々に入手が難しくなっているという現状があります。
中国製の硯を一般に唐硯と呼んでいるのに対して、国産の硯は和硯と呼びます。和硯は唐硯に較べて値段も安く、気軽に使えるという点で、初心者にはかえって手軽な硯です。石質の点については、唐硯に較べてやや劣るのはやむをえないとしても、丹念に探せば、かなり質の高いものを見つけることができます。和硯でいちばん名の知られているのが玄昌石(げんしょうせき)で、これは宮城県雄勝(おがち)産で、自然石で造った硯としては最も普及しています。
かつては「赤間か雨畑か」といわれたほど山口県赤間産の硯石と山梨県雨畑産の硯石は良質なものとして玄昌石と並んで有名でした。しかし現在では、良材の入手が難しく、新しい硯を造ることは、ほとんどできなくなっている状態です。このほかに、正法寺石(岩手県)、竜渓石(長野県)、若田石(対馬)などの名も知られています。
(2)良い硯の見分けかた
墨がなぜ下りるのかというと、硯面に鋒鋩(ほうぼう)といって、ヤスリ目のような凸凹があり、墨を磨ると墨の粒子がそれにひっかかってバラバラにほぐれるからです。墨水はその粒子が水とまざったものです。この鋒鋩の状態の良否によって、得られる墨水の性質が変わってくるわけですから、実用硯としては、まず鋒鋩の状態のよいものを探さなければなりません。
なお、硯は使ったまま放置しておきますと墨が固まってしまい、以後、墨を下ろすさまたげになりますので、使用感は必ずよく水洗いする習慣をつけてください。